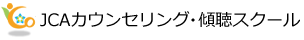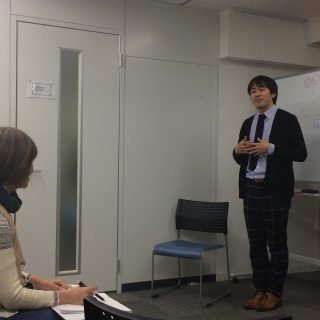5/12・13は、心理ケアカウンセラー資格認定講座でした。
今回のテーマは、「ほめる」と「ねぎらい」でした。
この違いは、こちらの記事でお話をしていますので割愛しますね。
さて、褒めるコミュニケーションは僕もカウンセリング中に意図的にすることがあります。
チャレンジしたことやできたことに対して、「すごいですね!」と褒めたり、
「何か工夫したんですか?」とうまくいった理由や、自分なりの努力に目を向けてもらったり
といったようにです。
人は褒められるとうれしいものですし、もっとやってみよう!と力が湧いてくるものですよね。
そして出来たという経験を積み重ねることで、自己効力感が高まってきます。
自己効力感とは、何か行動をするときに感じる「できる」という感覚のことです。
例えば、野球はやったことが無いけれど同じ球技だしできるだろうというのもそうですし、
仕事を依頼された時に、これくらいならできるとかそういった感覚のことがこれにあたります。
なぜこのお話をしているかというと、
悩んでいる方というのは自己効力感が一時的に落ちている場合が多くありますから、
できるという実感を高めてもらう関わり方が重要だったりするのです。
そこでその一つの関わり方として、褒めるというコミュニケーションが有効なのです。
褒めることで、できていることに目を向けてもらったり、
本人が過小評価している行動に対して正しく評価できるように励ましたり、
そういったことを通して、「自分はできているのだ。」という実感を高めてもらう関わりができます。
また、こんな褒め方をすることがあります。
例えば、「人の気持ちを理解したい。」という悩みを持っている方の相談を受ける場合、
その方がカウンセラーの気持ちを汲み取ったりした場合に、
「今仰っていただいた言葉は、よく私の気持ちを表しています。すごいですね!きちんと汲み取れていますね。」
といったように、その場でそういう理解する発言が出たときに褒めることがあります。
こういったケースですと、悩みを抱えている方は自分が「達成したい課題」をどれくらいできているのか、
その判断基準もわからないことが多いですし、自分が出来ているという「実感」が乏しい場合がありますから、
褒めるというコミュニケーションで、その方向性で大丈夫ですよ、
きっちりとできていますよということを伝えることで、その行動(この場合は言動)がもっと出るように励ますことが大切になります。
そうすることで、もっと汲み取ろう・理解しようという気持ちが出てきますから、
自分の達成したい課題に取り組む意欲が上がり、望ましい行動をもっととろうと思うようになるのです。
さらにその結果として上手くいけば、自分はできるんだという自己効力感が高まり、自信へと繋がっていくのです。
このように悩んでいる方で、著しく自己効力感が落ちている方に対しては、褒めるコミュニケーションによって事効力感を高めてもらう取り組みや、本当に小さい今から出来る行動をして、小さな成功を積み重ねて出来るという実感を高めてもらう関わり方が大切となるのです。
先日の心理ケアカウンセラー資格認定講座では、そのようなお話もさせて頂きました。
そして自信には、実はもうひとつの感情が関わってきます。
それは自尊感情です。
自尊感情とは、自分を大切に思う気持ちのことですが、
今回はちょっと長くなったのでこのお話はまた次回にしますね!
心理ケアカウンセラー資格認定講座 次回は10/13(土)スタートです。